ネットで妙な記事を見かけてお茶を吹き出しそうになったw
ネット上では蓄財や資産形成を啓発するような情報が溢れています。
今回は富松が目にした妙な蓄財啓発記事に関して思う所を書こうと思います。
タイトルの破壊力が凄いw
「「1000万円の貯金がある人」と「毎月5万円ずつ貯める人」、どっちが30年後リッチになる?」というタイトルの記事なのですが、この時点で既にヤバい破壊力がありますねw
ただの掛け算の問題w
「貯金」、「円」というキーワードから円建て預金の利回りはほぼゼロなので、タイトルの時点で答え出てるじゃんと思いましたが、とりあえず内容を読んでみました。
要約すると以下の内容。
- 毎月5万円を30年間貯めると30年後には1800万円になる(だから1000万円持ってる人よりリッチ)
- 今は低金利時代だけど利回りのよい商品があったら利息も増える(毎月5万円だと金利1%で2098万円、3%で2913万円になるけど、初期1000万円の人だと金利1%で1347万円、3%で2427万円にしかならないので、毎月5万円の勝利)
- 筆者は若い時に郵便局で貯蓄性のある保険に入ってコツコツ保険料を払っていたら1000万円貯まった
- だからみんなコツコツ貯金しましょう
結論はいいとしても、ツッコミどころ満載ですw
ツッコミ1:なぜ1000万円持っている人は貯蓄や資産運用を継続しないのか
記事では開幕貯金1000万円ある人は何もせず、貯金ゼロの人が毎月コツコツ5万円を貯蓄していき、30年後に1800万円を蓄えるというサクセスストーリー(笑)になっています。
しかし、現実では貯金1000万円を持つ人というのは、結構マトモな金融リテラシーを持っていることが多く、そんな人が30年間もボ~っとして貯金ゼロだった人に追い抜かれるというのは中々考えにくい状況ですw
ツッコミ2:税金の考慮が入っていない
記事では「金利1%で2098万円、3%で2913万円」という記載がありますが、この金額は金融資産から発生する所得に対する税金(20.315%)の考慮が入っていません。
金融商品にもよりますが、毎年の税金が発生する前提で計算すると以下になります。
金利1%:2098万円 → 2017万円
金利3%:2913万円 → 2561万円
金利が上がるほど、税金による影響が大きくなるので(勝負云々以前に)無視できる要素ではないですね。
ツッコミ3:本当に貯金1000万円の人は勝てないの?
そもそも元金(初期1000万円 VS 30年積み立て1800万円)の時点で1.8倍もあるこの理不尽な勝負(笑)、貯金1000万円の人には勝ち目がないのでしょうか?
いや、普通に勝てますよw
積立の人は月5万円の積み立てなので、年間の元金増加額は60万円です。
貯金1000万円ある人は元金1000万円の年利回りで60万円以上(年利回り6%以上)で運用する前提だと、毎月5万円の積み立ての人に勝てることになります。
例えば、S&P500インデックスの過去平均リターンは7%なので、(そのリターンが継続する前提だと)貯金ではなくS&P500インデックスファンドへの積み立てを行うことで勝負の結果は一変します。
貯金1000万円の人がS&P500に投資して30年後:4826万円
毎月5万円をS&P500に積立投資して30年後:4300万円
もちろん税引き後の結果ですよw
「コツコツ貯金する」という行為を礼賛し、貯蓄できない人を啓蒙するために、元金に2倍近くも大きな下駄を履かせたつもりだったのでしょうが、資本主義の世界はそんなに甘くないのですw
だから格差拡大が止まらないって世界中で言われてるのですw
ツッコミ4: 貯蓄性や投資性を持つ保険のパフォーマンスは良くない
筆者は「若い時に郵便局で貯蓄性のある保険に入ってコツコツ保険料を払っていたら1000万円たまった」といった内容の体験談を記載していますが、自分で貯蓄や資産運用を行ったほうがもっと早く1000万円たまる可能性が高いことを指摘したいですね。
なぜなら、保険に対して貯蓄性や投資性の機能が追加されると、それぞれに対して運用手数料がのしかかる為、自分で運用するよりパフォーマンスが落ちてしまうからです。
そもそも「貯蓄・資産運用」は「保険」とは目的が異なるので切り離して考えないと、(保険で運用してしまうと)資金拘束の影響が思わぬリスクとなってしまう事もあり、その可能性を無視すべきではないのです。
「投資や貯蓄を保険に丸投げ」は保険会社にとって「最上級のカモ」になるので気を付けましょうw
まとめ
久しぶりにとても面白い記事を読みましたw
メチャクチャお膳立てされた出来レースで、結果が逆転することもあるというw
お金の世界は奥が深いねww
情報には「正しい情報」と「間違った情報」があるのですが、「100%正しい」とか「100%間違っている」という情報は滅多にありません。
むしろ「半分正しい」とか「20%間違っている」というようなグレーな情報が多いものなので、読み手も与えられた情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分なりによく咀嚼してから飲み込むようにしましょうw
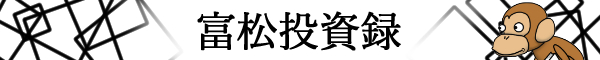



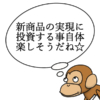


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません